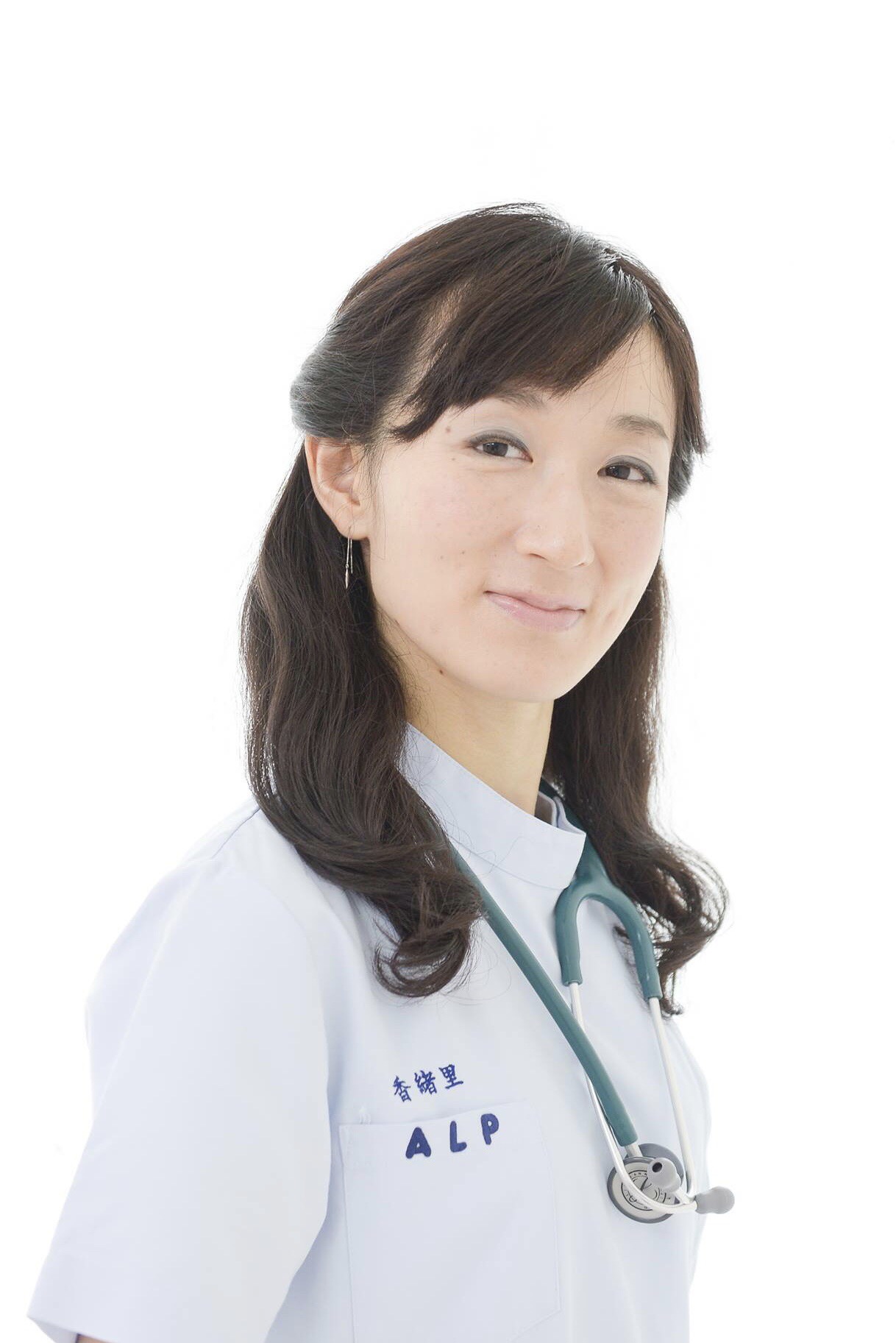【獣医師監修】ペットの認知症について解説
ペットも人と同じようにの高齢化が進み、犬や猫における認知症が増えてきています。
今回は、ペットの認知症について解説します。ぜひ最後までご覧ください。
ペットの年齢

犬や猫は人よりも早く歳をとります。
「高齢」といわれる年齢は、動物種や品種、生活環境などにより異なりますが、一般にペットが高齢になると、視力、聴力、嗅覚などの感覚が衰え、動きが鈍くなり、睡眠や休憩している時間が長くなります。
日常的に散歩や運動をする犬では、散歩に行きたがらなかったり、運動を嫌がることもあるので、注意が必要です。
ペットと人の年齢をみると、犬猫の1歳は、人の年齢に換算すると15歳となります。また、犬の年齢は、大型犬や小型犬などサイズによっても違います。
ペットの年齢について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください
https://www.wepet.jp/knowledge/8835/
ペットの認知症
認知症は、認知機能不全(高齢性認知機能不全/認知機能不全 症候群)といい、明確には定義されていませんが、小澤(2020)の論文では、「高齢期に認知機能が緩徐に低下していき,その結果複数の特徴的な行動障害を呈するようになる犬と猫の症候群である。」としています。
犬の認知機能不全の発生率はばらつきがあるものの加齢とともに高まり、14〜15歳以上が高くなります。
カリフォルニア大学の研究者の調査では11〜12歳の10%、15~16歳の35%に2つ以上の行動障害が認められました。
猫の調査は少ないものの11~15歳の猫の28%、15歳以上の約50%が認知機能不全の症候を1つ以上あるという報告があります。
認知症は、脳の老化に伴い認知機能が低下し、日常生活に支障をきたす状態をいいます。発症すると行動や性格に変化が見られるようになります。
- 異常な食欲
- 無目的な吠え
- 飼い主の姿が見えなくなると鳴く
- 無目的に歩き続ける
- 不適切な排泄 など
といった様々な症状が現れます。
他にも、飼い主や他の動物に対する反応が鈍くなり、呼びかけに応じなくなったり、逆に攻撃的になることがあります。自分の居場所や周囲の環境が把握できなくなり、家具にぶつかったり、トイレの場所を忘れたり、排泄の失敗が増えることもあります。
高齢のペットに急激な環境の変化はよくありませんが、生活に刺激があると認知症は進みにくいと言われます。
原因と予防
認知症の明確な原因は完全には解明されていませんが、脳の萎縮などが関与していると考えられています。
特定の犬種・猫種だけが起こる訳ではないため、全ての飼い主が意識する必要があります。
予防するためには、飼い主とのふれあいを好むペットにはゆったりとしたスキンシップやブラッシングをしたり、一緒に簡単なゲームをするなど体と心にほどよい刺を与えるといいでしょう。
おもちゃで遊ばせたり、宝探しゲームをすることで、脳を活性化させたり、日中に散歩や遊びで適度な刺激を与え、夜間の睡眠を促進するのも有効です。
また、抗酸化作用や抗炎症作用のある成分を含むサプリメントが、脳の老化を緩やかにするとされています。
まとめ

ペットの認知症は完全に防ぐことは難しいですが、日々のケアや環境整備によって進行を遅らせることができます。
愛情を持って接し、ペットが安心して過ごせる環境を整えることが大切です。
参考文献:
環境省「ペットも歳をとります」
小澤真希子(2020)「犬と猫の高齢性認知機能不全」動物臨床医学,29(3),101-107
Zesty Paws
監修獣医師:丸田 香緒里
◆丸田 香緒里 プロフィール
日本大学卒。動物病院勤務後、「人も動物も幸せな生活が送れるためのサポート」をモットーにAnimal Life Partner設立。ペット栄養管理士、ホリスティックケア・カウンセラー、メンタルケアカウンセラーなどの資格を生かし、病院での診療や往診のほかに、セミナー講師やカウンセリング、企業顧問、製品開発など活動は多岐にわたる。
HP:http://animallifepartner.com/